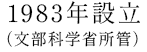生涯学習講演会レポート
多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ第33回
社会課題をおもしろがりながら
ゆるやかに変えていくための意味と仕組み
―「鳥の劇場」の事例から社会やコミュニティとの関わりを考える―
- 講演者:
- 中島 諒人 (鳥の劇場 芸術監督)
- 聞き手:
- 苅宿 俊文(青山学院大学社会情報学部プロジェクト教授)
会場:オンライン開催(ZOOM)
鳥取県鳥取市鹿野町の廃校を活用した「鳥の劇場」
苅宿:今日は鳥の劇場の中島さんにお越しいただきました。中島さんの展開されていることは、分野こそ演劇なんですけれども、いろいろな場づくりや人づくり、組織づくりの展望や戦略を考えていく上でもヒントになることが埋めこまれているなと私は考えています。
今日のタイトルは「社会課題をおもしろがりながら、ゆるやかに変えていくための意味と仕組み」。今日いらしている方々の現場の課題は、何らかの社会的な課題に繋がっているとみることができると思うんですね。その課題に義務的に取り組むのではなくて、どこかおもしろがりながら、いわゆるポジティブに能動的に動きながら、ゆるやかに変えていくということを考えてみたいんです。中島さんとは長いお付き合いになりますけれど、実際に人口減少地域にポツンと劇場をつくり、年を重ねていくごとに、緩やかに地域が変わり、その周辺が変わり、さらに私たちへと刺激が広がっていっています。やはり、そこには時間が積み重なるということが不可欠と捉えていて、効率性を求めない、こういうやり方もあるんだなというようなことを感じていただければと思います。
では中島さん、よろしくお願いいたします。
中島:はい、よろしくお願いします。まずはちょっと活動の概要をご紹介すると、鳥取県鳥取市鹿野町の廃校になった小学校と幼稚園を「鳥の劇場」という劇場に変えて、2006年から展開しております。元は体育館だったところを半分にして200席の劇場に、幼稚園の遊戯室をホワイエとして前室にしたり、屋外のグラウンドで野外の舞台をつくったりっていうことを、基本的にはやっています。


この劇場を軸としながら、いくつかやっている事業というのがあって、そのひとつが「鳥の演劇祭」です。今年も9月13日から29日まで開催していたのですが、こちらは2008年からやっていて、2009年からは海外の劇団も招くようにしています。城下町である鹿野町の街中に複数の小さな仮設劇場をつくって、のどかな風景の中で、いろんな国から来た演劇を楽しめるみたいな企画です。今年で言えば、スコットランドの音楽劇、トランスジェンダーをテーマにしたブラジル出身のサーカス・アーティストの作品、フィンランドから来た人形劇……それから名物企画として、鹿野町のお年寄りの一代記みたいなものをですね、本人から聞いた話を何場面かの芝居にして、街中を回遊しながら見ていただく「鹿野タイムスリップツアー」なんかもあります。ほかにも若いアーティストに滞在制作をしてもらうアーティストインレジデンスを展開したり、週末にはアーティストと観客を交えたパーティをしたり、そんな演劇祭です。今年の演劇祭のテーマは「いろいろである いろいろであれ」。日本という国の見えない掟のようなルールが私たちの多様なありようを縛り付けている部分があるんじゃないかと。それを自由にしていくことを目指して、そもそも私たちは多様であって、もっと多様性を出していこうという願いをタイトルに込めました。
演劇祭のほかには、鹿野学園という小中一貫校で演劇ワークショップを授業として行ったり、演劇に興味がある子供たちに自分たちの手でお芝居をつくってもらう「小鳥の学校」も展開しています。それから、障害のある方を対象にした「じゆう劇場」というプロジェクトもあります。もともと社会と演劇との関わりを面白い形で示せるチャンスがあれば、基本的にはやったことがないことでも断るまいという姿勢でおりましてですね、障害のある人と演劇をつくってほしいという依頼を受けて、2013年からずっと継続をしております。障害のある人、ない人が一緒にお芝居をつくるってことを大事にしていて、劇場で上演したり、巡回公演をしたり、それから学校公演をしたりもします。障害のある人の演劇というと、どうしたって子供たちも構えてしまうんですが、「あれ? なんか面白いじゃん」という感じで壁が消えていく。その後でコミュニケーションの時間をとることで、障害への考え方が根本的なところで変わっていくというような体験をしてもらったりしています。
人口減少著しい鳥取で、「鳥の劇場」を始めた理由
苅宿:ありがとうございます。いろいろな社会的課題の解決に繋がることを、演劇を通してやってらっしゃるわけですが、それも鳥取県っていう人口減少地域、しかも街中ではなくて、田んぼや畑に囲まれている地域の中でなさっている。そもそも鳥取で鳥の劇場を始められた理由はなんだったんでしょうか。
中島:私は、生まれは鳥取なのですが、大学は東京でですね。私が東京にいた頃って、いわゆる下北沢の小劇場演劇とかが非常に流行っていた時代だったんですね。大学のサークルで演劇をはじめて、そのままズルズルと続けていく中で、サブカルや富裕層の嗜好品と位置付けられがちな日本とは違う、ヨーロッパの演劇のあり方に憧れをもつようになっていったんです。各地域に劇場があって、コミュニティのなかの公共財として位置づけられているというあり方ですね。そこからよくよく考えているときに、郷里である鳥取に思い至りました。53万人をきる全国の人口最小県で、鳥取市で言えば、20年前に出生数2000人だったのが、今では半分になっている。そういう人口減少の地域でやるっていうのは面白いかもなと思ったんです。鹿野町を訪れたことはなかったんですけれど、非常に良い出会いがあって、鹿野町で始めることになりました。
苅宿:人口減少を、将来的にお客さんいなくなるからやばいなと思うんではなくて、面白いなと思ったと。どんな面白さがあると思われたんですか。
中島:鳥の劇場を始めたのは、私が40歳のときでした。40で始めるということは、もうこれで食っていくしかない。劇団メンバーも結構、鳥取に来てくれていたので、みんなが食っていける状況をつくるしかないと。夢でワクワクしている部分と、現実的にどうするんだっていう部分はありました。というのも、一部の例外はありますけれど、大半の演劇がですね、チケット料収入だけではPayをしないという現実があるんです。世界中を見渡しても、何らかの補助金だとか寄付だとかによって、活動が持続されているっていうのが現実です。そんな状況下で、しかも鳥取で続けていくならば、安定的に補助金を得る、何らかの形で社会と取引できる形をつくらなければいけないと考えていました。「演劇は、社会課題に対してこういう貢献ができます」といって、「なるほど、それは社会にとって意味があるものですね。であれば、この補助金を出します」っていうような、取引関係みたいなものがつくれなければ、活動が維持できないなと。そう考えたときに、鳥取県が抱える人口減少、高齢化、加えて山陰、“陰”と言われることに甘んじる自信のなさみたいなところに対して、演劇が貢献していくというストーリーが逆につくりやすいかもしれないと思ったんです。
演劇活動を、社会的な意味につなげるための「言語化」と「発信」
苅宿:そうすると、自分たちが突き詰めてやりたいことと、社会に還元しなきゃいけないこととが出てくるのかなと思うんですけれども。演劇祭や、学校でのワークショップ、障害者との演劇プロジェクトというものは、ある意味で演劇の本質でもあるけれども、同時に社会的な課題に繋げていく意思もあったということでよろしいんですか。
中島:そうですね。例えば、演劇祭っていうのは社会的に見ると地域振興ですよね。地域振興っていうのは、一番シンプルには動員数と、そこでお金がいくら落ちたかっていうことに集約される。しかし残念ながら、 演劇祭で1万人動員するっていうことはできないんです。これはもうキャパシティの問題で、演劇の宿命ですね。チケット料も、4人家族で来て、ご飯代もふくめて1日1万円以下になる設定にしたいと思うと、それほど高くはできない。動員数もチケット収入も、高い目標設定ができないんです。
それでも、自分がやりたくて、やる価値があることだと思って、やっているんですね。地方の山間の劇場に、世界から多様な舞台作品が来て、そこに出会いや交流が生まれる。田舎の閉鎖性とは真逆のことが起きる。そういう量的にはわずかでも、質的には良いということ、その意味をどう伝えていくかが重要になってきます。意味を言語化することが重要で、新聞やメディアを通じて発信していく。今ではフランスや韓国をはじめとして、海外での認知も上がってきているんですが、単純な数字的な評価で消費されてしまわないようにしていくってことが重要なんです。障害のある人と一緒にやる「じゆう劇場」もそうです。もちろん、当事者の満足も大事にするんだけれども、活動を発信していくことを通じて、差別のない社会、人と人とが魂を混ぜ合わせるとはどういうことか、積極的に発信していく。本当に微力ですけれどね、少しずつでも社会がより良いものになっていくようにしていこうと目標設定をして、どの事業においても、言語化と発信を常に念頭に置いているっていうことですね。

やりたいことをやる。意味のないことはやらない
苅宿:今の話って、ワークショップの領域でも同じで。活動としては小さくても、意味を言語化していくことは非常に重要だなと私も感じています。そうはいっても、ここまで長く、いろんなことが継続すると思ってらっしゃったんですか、正直なところ。
中島:「続くかな?」って思っていたら、おそらく始められなかった。やっぱり初めは、とにかくやれるっていうことが、もう嬉しくてしょうがなかったんですよね。だから演劇祭も、「こんなところに人が来てくれるぞ、海外からも来てくれるぞ、字幕はどうする!」みたいな高揚と失敗の連続で、本当によく続いたなと。鳥の劇場が続いた理由っていうのは、もう一番ドライな言い方をすると、「これで食ってるから、続けるしかない」ということだと思います。人間って、できるならば自分が一番得意なことで生きられたらうれしい。実際には、劇団員に月10万円しか渡せないときもあったんですよ。そのときに言っていたのが、「3つのことが大事だよね」ということでした。まず、やることがあるということ。人間、やることがないのは苦しいですから。それから、やっていることに誇りが持てるか。そして、それを喜んでくれる人がいるか。収入を増やす努力ももちろんしますが、実は我々が駆動していたのは、意味がないことをやりたくないということだったと思います。我々の活動は初めから、意味のあることだとみなが認識していた。これはこういう意味があるからやろう、こういう意味があるはずだからやろうと、手探りでやってきて、それは今も変わりません。なんていうかな、こういう形での活動の蓄積っていうのは、日本ではあまりないかもしれません。
苅宿:ある意味で、その場その場で考えていくっていうことと、やりたいことが前提だけれども、一方で意味のないことはやらないっていう前提もあると、そういうようなことがやっぱり大きいのかなって思いますね。外部要因、外からの評価として言えることはありますか?
中島:なるほどですね…僕らが活動を始めたころは、文化の東京一極集中っていうことに関して、やっぱり違うんじゃないのと、地方での芸術活動の意味が割と重視され始めた時代だったかなとは思います。もちろん先駆者としては、私の師匠でもある鈴木忠志さんが1976年から富山県の利賀村で活動されて、大きな灯台のような役割をしてくれていたり、日本の文化政策の中でもそういうところはあるかなと思うんですけれども。鳥の劇場を始めたころは、割とトレンドみたいになっていたかなと思います。人口減少の局面だからこそ地域が誇りを持ち、差別が横行する社会の中で多様性を大事にしながらコミュニティをつくっていくんだという。生産だけではない、いたわり合いだとか、他者の価値の尊重っていうことが、これからの社会の重要な要になっていくんだっていうようなこと、私たちの大義名分、活動の趣旨自体が大事なんだっていう。お客様の共感とか海外の演劇人からの評価とか、国とか県とか市からの評価というところもあるけど、やっぱり本質は何かっていうことと、それを我々自身が一番大事にしようとしてきたっていうところが、長く続いた要因かなと思いますけどね。
演劇人の資質「考えるよりやってみよう」がもたらすもの
苅宿:そうした価値観が共有できる劇団というか、チームみたいなものをつくって、維持するときに、なにが一番大事なポイントになるとお考えですか。
中島:なるほど。日常的には結構ね、すったもんだがあるんですよ。ついこのあいだも、「そんな話聞いてねえ」とかあるんですけど。ただ、私たちの特徴としては、芝居を一緒につくるんですね。そうすると、その瞬間にはみんなの気持ちがひとつになるんですよ。それぞれの日常っていうのは、いろいろなことが複雑に絡み合うから、対立も生じやすいんだけれども、芝居っていうみんなが共感できる、ひとつの方向に向かえるチャンネルがあるっていうことが、うちが続いているひとつのポイントかなと思います。
それから、演劇人の資質として、「考えるよりもやってみよう」みたいなところがあるんですね。もちろん何も考えないっていうことではなくて、例えば、うちの劇団の特徴として、小道具も衣装もなにもかも内部でつくるみたいな、実行力があるんですよ。ここぞっていうときの集団的な行動力がある。もちろん、さきほどから申し上げてきたような新しいことに挑戦するときには、いろいろ分かれるんです。意味がわかる人、わからない人、挑戦への不安が強い人、あまり不安がない人……表情を見てるとね、あまりポジティブに見えない人っていうのも必ず出てきます。でもね、「とはいえ、やろうぜ」っていう、“とりあえずやってみよう体質”みたいなのがあるので、しぶしぶでも「やってみるか」となることが多い。ただやっているうちに結構、ネガティブな反応だった人にも「ああ、なるほど、そういうことか」と、意味とか方法についての理解が遅れてついてくるんです。この理解の早い遅いっていうのは、良い悪いの問題じゃなくて、理解が後からついてきた人の意見が、先に理解していた人にとって、別の良い情報になって、ある種、全体的に知恵が高まっていくということが起こるんです。僕なんかは、とにかくやりたがりだから、「もういいから、やろうよ! なんでわかんないんだよ!」って内心思いながら、「まあ、やってみようよ~」みたいな感じではじめて、結果的にいろんなことができてきたっていう感じだと思いますね。
苅宿:最後に、なにか自分の持っているもので社会の役に立ちたいと思っている方、そういうような方の背中を押すとしたら、どのようなアドバイスをされますか。中島さんの約20年の経験を経て、感じておられることが、参考になるんじゃないかと。
中島:2006年に鳥の劇場をはじめて、ここまで続けてきたなかでいうと、僕の中ではやっぱりね、自分の感覚を信じるっていうことに尽きると思います。「これは面白いな。なぜなら、こうこうだからだ」みたいに自分の感覚を信じて、やってみる。悩んでいるより、とりあえずやってみたほうが良くて。つまり、悩んでいたら、失敗もできないじゃないですか。そもそも失敗ということも、全部が失敗ってことはほとんどなくて、それなりに良かったこともあり、それなりに良くなかったこともあるっていうことだと思うんです。だから、自分の感覚を信じて、失敗を恐れずに、やってみるっていうことの積み重ねが大事で、ここまでやれてきたのは、そういう感覚が僕の中でも集団の中でも共有されてきたっていうことなのかなと思います。
苅宿:僕が感じている中島さんはある意味、頑固者で、やりたがりで、だけれども惜しみなくシェアをするっていうことをなさっている方。そんな彼の姿、生き方が、今日いらしてくださっている方のヒントになるかなと思っています。中島さん、ありがとうございました。
【グループでの感想共有タイム】
【質疑応答】
※シンポジウムでは、グループ感想共有ののち質疑応答を行いました。