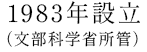2024(令和6)年度 選考決定証授与式
博士号取得支援事業 選考決定証授与式の様子と、合格者の皆さんのインタビューをご紹介します。

懇談タイム。合格者同士で刺激しあい仲間になっていく。
博士号取得支援決定をうけて
泉 有紀 (52歳)
東京大学大学院 医学系研究科/米国足病医
【研究テーマ】 足潰瘍に対する免荷療法活用促進を目的とした多職種連携教育プログラムの開発とその効果検証
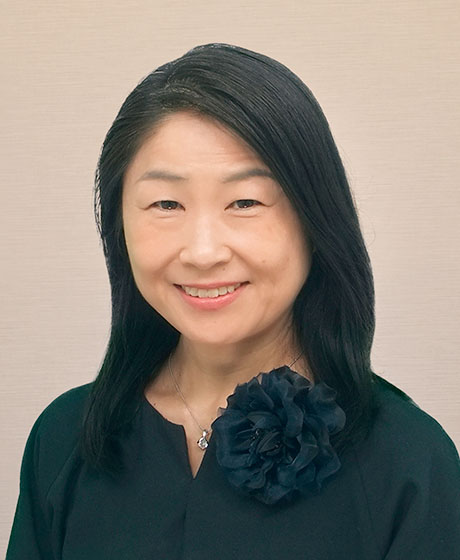
研究目的
足潰瘍は、糖尿病や動脈硬化によって足の血流が悪化し、皮膚が損傷しても治癒しにくくなる疾患。悪化すれば感染症や骨髄炎を引き起こし、最悪の場合、足の切断に至ることもある。傷が治っても、長期入院による身体の衰弱や認知症の発症という事態を招く例も多い。海外では、日常生活を送りながらも足底の創傷に体重がかからないようにして傷を治す「免荷療法」が一般的だ。泉氏は、日本在住唯一の米国足病医として「免荷療法を日本に広めるための多職種連携教育プログラム」を開発し、効果検証を行っている。プログラムは、特定の専門職対象ではなく、治療を行う同一院内の多様な専門・職種メンバーが一緒に学べることが特長。日本で免荷療法が身近になり、多くの患者の足潰瘍を救うことが期待される。
合格のコメント
今回の受賞は「さらに研究を深め、日本の医療現場に貢献しなさい」という励ましと受け止めました。今後も本教育プログラムを通じて、免荷療法だけでなく、足病分野における多職種連携の重要性を伝えていきたいと考えています。博士研究が終わった後も、まだまだやりたい研究がたくさんあるので、今後も教育と研究を通じて、一人でも多くの人が自分の足で歩き続けて暮らせるような活動を続けていきたいと思います。
岡田登貴(67歳)
大阪大学大学院 文学研究科
【研究テーマ】 本願寺坊官にして能役者下間少進仲之 の能

研究目的
本研究では、桃山期から江戸最初期の能役者であり、後進の育成にも力を注いだ下間少進仲之の能について考察する。少進自筆の上演記録『能之留帳』や能型付『童舞抄』を利用した研究はあるが、少進自身がどのような能を演じたかは充分に明らかにされていない。少進は金春流の素人能役者と言われているが、資料によると他流に通じる型なども演じている。本願寺坊官でもあった少進が、流儀の枠を超え、柔軟な革新性を持って能に取り組んでいたことを残された能型付などを用い、実証的に明らかにする。少進の能を考察することは、現代の能の新たな可能性にも通じ、ひいては演劇学の発展に寄与すると考える。
合格のコメント
社会課題を直接的に解決する研究ではないため、合格は予想外でうれしいです。下間少進研究で放送大学の修士課程を修了しましたが、10年を経て、十分にやりきれていない思いが生じました。仕事が一段落して探究心が再燃し、演劇学の博士後期課程に進んだ次第です。若い頃から演劇に興味があり、新劇の劇団にも属していました。能については最初は何を言っているかもわからないレベルでしたが、だんだんと好きになりました。現在も月に1、2回は舞台を観、能楽師のお話を聞くために謡の稽古も受けました。実践による理解を通し研究を進めたいです。
栗川 治(65歳)
立命館大学大学院 先端総合学術研究科/
立教大学コミュニティ福祉学部 兼任講師/東海大学文明研究所 研究員
2025年3月博士号取得
【研究テーマ】 「能力の社会モデル」に基づく「異在労働」評価システムの研究
――日本における障害のある教員の当事者運動の歴史から

研究目的
栗川氏は、22歳から60歳まで高校の教員を務め、そのうち30代からの約30年間を全盲の教員として教育にあたってきた。本研究は、障害を持つ教員を評価するシステムが日本でどのように形成・運用されてきたか、またそのシステムを障害を持つ教員がどう感じ向き合ってきたか、直面してきた歴史的背景を掘り下げ明らかにした。
第1の特長は、能力観のパラダイム転換である。能力は個人の知識やスキルなど属人的なものと考える「能力の個人モデル」から、他社と共存・協働する相互関係における役割の発揮と捉える「能力の社会モデル」への移行・拡張が必要であるとする。
第2に「異在労働」という概念の提示。健常者の労働を標準とし、障害者の労働はその軽減と見なすのではなく、障害に応じた異なる在り方ととらえ、障害のある教員の役割や評価の再構築を提案する。
合格のコメント
あまり事例がない研究が評価されたことに大変感謝しています。大学院進学は学部卒業時に失敗しあきらめていたのですが、59歳で再挑戦し夢が叶いました。調査過程で文献を読むためにリサーチアシスタントの支援が大いに役立ちましたが、その費用にもあてられます。今後は、教育現場以外の民間企業や海外の状況にも調査・研究を広げていきたいと思っています。
田代昌彦 (56歳)
東京都立大学大学院 経営学研究科/三条市立大学講師
【研究テーマ】 技術(イノベーション)と社会の関係性分析

研究目的
田代氏は長く製薬会社に在籍した。医療は患者のQOL(生活の質)を改善する一方で、副反応による健康被害問題を引き起こす場合もある。新規医薬品/医療技術が、どのように社会を変化させ、逆に社会から影響を受けた技術がどのように変容するかを、経営学的視点で研究している。医療技術のシーズは単にアカデミアや製薬企業などから創出されるだけでは無く、社会からの複雑な関与も受けて生み出される。医療に関わるステークホルダー(患者、医療関係者、アカデミア、産業界、規制当局、マスコミ、法曹界など)を研究対象とし、1次/2次データの定性/定量分析を通して新しい発見事実や理論貢献を見いだし、医療イノベーション研究の発展に寄与したいと考えている。
合格のコメント
製薬会社での勤務において、理系の知識だけでは業務を取り回すことに不十分と感じるようになり、40代半ばで経営学の大学院に進みました。修士論文を執筆し終えた際、医療を題材とした研究に未練が残り、まだ間に合うと博士課程に進みました。一番苦労したことは、学会誌への論文投稿(査読)です。査読が通らず本当に苦しみましたが、試行錯誤を繰り返して乗り越え、採用に至った時の喜びは大きかったです。現在は大学教員として奉職しています。地域貢献、研究、学生指導に力を注いで参ります。
橘 昌尚(52歳)
和歌山大学大学院 観光学研究科/新潟県職員
【研究テーマ】酒蔵ツーリズムの推進・発展における観光地域づくり法人(DMO)の役割

研究目的
日本には北から南まで全国に約1,500の日本酒の酒蔵がある。また、その酒蔵の多くは地方に存在しており、それらの酒蔵や酒蔵での試飲体験などと周辺の観光資源を組み合わせた酒蔵ツーリズムの推進が各地で行われている。酒蔵は、古い歴史を持つものも多く、伝統的な蔵造りの建物が文化財に登録されるなど、地域文化を伝承する役割を担っていることから、酒蔵ツーリズムは新たな観光の形態として期待されている。観光地域づくり法人(DMO)が、酒蔵ツーリズムを通じて、マーケティングやマネジメントの視点から、地域活性化にどのように貢献し、どういった役割を果たしているかを検証することが本研究の目的である。
合格のコメント
合格できたことを大変光栄に思います。授与式後の歓談でさまざまな分野の研究者との交流ができたことをうれしく感じており、今後の学びに大きな期待をしています。私の研究が、酒蔵ツーリズムをはじめとしたコンテンツツーリズムの推進・発展について新しい知見を提供できれば嬉しく思います。博士の会では、新潟のお酒を持参して、皆さんと楽しく意見交換できることを楽しみにしています。研究を通じて、地方経済の活性化に貢献できれば幸いです。
飛田八千代(55歳)
筑波大学 理工情報生命学術院/東京外語大学AA研 共同研究員
【研究テーマ】 アフリカ都市部における「共食」を中心とした食料消費行動に関する実証研究
―共食に着目した新しいフードシステムを目指して―

研究目的
アフリカ諸国は、2000年以降の爆発的人口増加により、急速な都市化と食事の嗜好変化が起きているが、食料生産性が低いことから、主食の多くを海外輸入へ依存している。さらに、貧困や脆弱な社会保障制度ゆえに、食料に十分アクセスできない割合が58%と世界で最も多い。そんな中、飛田氏は滞在したセネガルの都市部において、家族、友人、隣人、施しを求める少年たちをも含めて食事をともにする「共食」の習慣に着目した。研究は、セネガルでの調査結果を基に、都市住民による共食が都市のフードセキュリティに果たす役割を解明する。公的社会保障が不十分な中でも、食を通じたインフォーマルな人間関係がフードセキュリティを支えている可能性がある。共食が持つ相互扶助的な側面を再評価し、アフリカの持続可能なフードシステムの構築に向けた示唆を与えることを目指す。
合格のコメント
私の研究が、アフリカの人々が直面している食料の課題解決に貢献できることを願っています。特に、アフリカ食文化の特徴である、共食の概念を活かした新しいアプローチを提案したいと思います。修士課程では分析能力が足りず納得のいく研究が出来ませんでした。その悔しさと、調査協力してくれた現地の人たちの姿を社会に伝えるため博士号を目指しました。今後もアフリカと関わり続けて役立ちたいと考えています。
*敬称略
*五十音順、年齢は授与式当日
*「研究テーマ」は応募時のものです。
博士号取得支援 アーカイブ
- 2024年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー
- 2023年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー
- 2022年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー
- 2021年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2020年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2019年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2018年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2017年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2016年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2015年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)
- 2014年度 博士号取得支援授与式レポート・インタビュー(PDF)